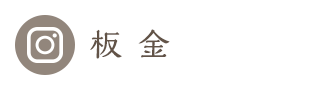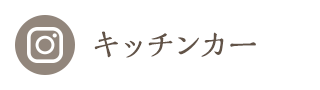皆さんこんにちは。
三重板金工業の更新担当の中西です。
~“軽い”だけじゃない、“強くて賢い”時代へ✨~
寺社の銅板葺きから、明治以後の金属屋根の広がり、戦後のトタン普及までを追いました
板金工事業が「雨を止める職人仕事」から、
**省エネ・耐久・防災・リフォームを支える“高性能屋根産業”**へ進化していく歴史です⚡
目次
1)塗装鋼板の進化:板金は“サビとの戦い”を技術で乗り越えてきた️
トタンが普及すると、次に課題になるのがサビ(腐食)です。
そこで重要になるのが、表面処理と塗装技術。鋼板メーカーの技術史では、1970年代以降の塗装鋼板の開発・商品化が時系列で示されています(例:1973年にふっ素樹脂塗装鋼板の日本初商品化など)。
ここで板金工事の価値は、材料の性能向上と一緒に引き上がります
-
より長持ちする
-
メンテ周期が伸びる
-
色や意匠の幅が広がる
-
住宅にも工場にも適用しやすい
つまり板金工事は、現場の腕だけでなく、材料技術の進歩を取り込みながら発展した産業なんです
2)ガルバリウム鋼板の登場:金属屋根の“主役交代”が始まる✨
屋根板金の歴史で最大級の転換点が、ガルバリウム鋼板(55%Al-Zn合金めっき鋼板)の普及です。
ガルバリウム鋼板は1972年に米国で開発された、とする解説があり、日本では1982年に日本初の商品化(高耐食性めっき鋼板として)を示すメーカーの技術史も確認できます。
ガルバがもたらしたインパクトはこれ
✅ 耐食性(サビに強い)
✅ 軽量(建物にやさしい)
✅ リフォーム適性(カバー工法などと相性が良い)
✅ 雪・沿岸など過酷環境でも選ばれやすい
これにより、板金工事業は「トタンを張る仕事」から、
高耐久・長寿命の屋根を設計して提案する仕事へ進んでいきます✨
3)工法の進化:縦ハゼ・立平・折板…“水を止める仕組み”が洗練される
材料が良くなると、次に勝負を決めるのは工法です。
板金屋根は、ただ張るのではなく、雨仕舞の仕組みを作る。
そして工法は、時代とともに洗練されていきました。
-
立平(たてひら)・縦ハゼ系:釘穴を減らし、防水性を高めやすい⬇️
-
折板屋根:工場・倉庫など大スパンを支える
-
役物(やくもの)加工:棟・谷・ケラバ・軒先の納まりで品質が決まる
この頃から、板金工事は“雨漏り修理屋さん”という枠を超え、
屋根というシステムを組み上げる施工技術へと格上げされていきます✨
4)リフォーム市場の拡大:板金工事業は「守りの産業」から「再生の産業」へ
日本の住宅は、建てて終わりではなく「維持して住み続ける」時代に入ります。
ここで板金工事業は、リフォーム・改修の主役になります
特に大きいのが
-
雨漏りの予防(早期点検・部分補修)☔️
-
葺き替え(屋根の寿命更新)
-
カバー工法(既存屋根の上から新しい金属屋根を施工)➕
-
断熱材一体型・遮熱などの快適性アップ
板金工事の価値は「新築で一回」ではなく、
住まいのライフサイクルを支える仕事へと変わっていきます。
5)省エネ・快適の時代:屋根は“暑さ対策”の最前線になる➡️
夏の暑さが厳しくなるほど、屋根の役割は大きくなります。
遮熱塗装鋼板のように、機能性を持たせた塗装鋼板が商品化されてきた流れも、メーカーの技術史で示されています。
屋根板金工事はここで、
-
遮熱(熱を入れにくくする)
-
断熱(熱を伝えにくくする)
-
通気(屋根裏の熱を逃がす)
という“住宅性能の領域”と深く結びつきます✨
つまり板金工事は、
雨仕舞だけでなく、暮らしの体感を変える工事になっていくんです
6)未来へ:次世代鋼板・DX・点検技術で、板金工事はもっと強くなる️
材料技術は今も進化しています。たとえば、ガルバリウム鋼板にMgを添加した次世代材(日本初商品化)といった流れがメーカー技術史に示されています。
また現場側でも、ドローン点検・写真管理・施工記録のデジタル化など、“見える化”が進んでいます
これから板金工事業に求められるのは、
-
高耐久材の正しい使い分け
-
雨仕舞ディテールの標準化+職人精度
-
防災(風・飛来物・雪)への対応
-
省エネ・快適提案(遮熱・断熱・通気)
-
施工品質の記録と保証(信頼づくり)
こうした「総合力」です✨
屋根板金工事業は“金属×工法×性能”で進化してきた➡️➡️
-
1970年代以降、塗装鋼板など表面処理技術が進み
-
1972年開発・1982年国内商品化などを経てガルバが広がり
-
工法が洗練され、リフォームで「再生の産業」へ
-
省エネ・遮熱・断熱で“住まい性能”の中核へ
-
次世代材やDXで、さらに信頼と価値が高まっていく
屋根板金工事業の歴史は、
「雨を止める」から「暮らしを守り、性能を上げ、家を長持ちさせる」へ進化してきた歴史です✨